2017年11月16日 22:53
運び≫
カテゴリー │中区H・U様邸
U様邸
刻みが終わり、
きれいに積みなおして、
シートで養生します。

材木屋さんのトラックに積み込みます。

もう一台。

小栗建築は細かい材料を。

現場に到着したら、クレーンでおろします。

透明のシートでそれぞれ養生してありますが、
念のためブルーシートでさらに養生

ひとつひとつ丁寧に。

今回はここまでやって半日です。
フォークリフトやクレーンがあるので、はかどります。
昔は全て人力だったそうで、
かなりの大仕事だったようです。
材木屋さんは、担いで運ぶので、
肩に毛が生えてくるほどだそうです。
そう考えると、今の職人は
とても快適な環境で仕事ができるようになったのかもしれません。
重機や電動工具が増えた半面、
怪我には気を付けないといけませんが。
本日も読んでいただきありがとうございます。
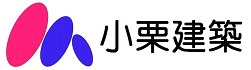
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
刻みが終わり、
きれいに積みなおして、
シートで養生します。
材木屋さんのトラックに積み込みます。
もう一台。
小栗建築は細かい材料を。
現場に到着したら、クレーンでおろします。
透明のシートでそれぞれ養生してありますが、
念のためブルーシートでさらに養生
ひとつひとつ丁寧に。
今回はここまでやって半日です。
フォークリフトやクレーンがあるので、はかどります。
昔は全て人力だったそうで、
かなりの大仕事だったようです。
材木屋さんは、担いで運ぶので、
肩に毛が生えてくるほどだそうです。
そう考えると、今の職人は
とても快適な環境で仕事ができるようになったのかもしれません。
重機や電動工具が増えた半面、
怪我には気を付けないといけませんが。
本日も読んでいただきありがとうございます。
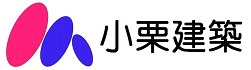
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
2017年11月14日 19:05
土台据え≫
カテゴリー │中区H・U様邸
U様邸
刻みが終盤になってくると、
次は建前の準備です。
天気とにらめっこして、土台の据付けです。
完成した基礎に基準となる墨を出して、
材料を配り、ボルトの穴をあけます。
そして、防腐剤を塗っておさめていきます。

多少雨に濡れても問題ありませんが、
この時は台風が近かったので、
念のためブルーシートで養生しました。

本日も読んでいただきありがとうございます。
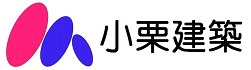
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
刻みが終盤になってくると、
次は建前の準備です。
天気とにらめっこして、土台の据付けです。
完成した基礎に基準となる墨を出して、
材料を配り、ボルトの穴をあけます。
そして、防腐剤を塗っておさめていきます。
多少雨に濡れても問題ありませんが、
この時は台風が近かったので、
念のためブルーシートで養生しました。
本日も読んでいただきありがとうございます。
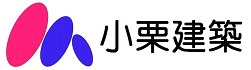
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
2017年11月11日 18:14
大黒柱≫
カテゴリー │中区H・U様邸
U様邸
今回LDKが広いので、キッチン横に大黒柱を配置しました。
搬入された柱は荒木と言って、
大雑把に製材した状態で搬入されてきます。(一番右)
普通の柱の4本分の太さがあります。

まずは下処理
柱には、化粧面が乾燥して割れてしまわないように
「背割り」と言って、わざと切り込みを入れてあります。
年月が経過すると、その切込みが広がるように柱が動くので、
くさびを打って、事前に広げておきます。

余分な部分を切り落とし、

手押しと自動(大型の機械)で形を整えます。
そこに溝をついて、

埋木してあげます。
下処理が終わったら墨付けです。


ほぞを付けてあげます。(これは上の部分で梁にささります。)

下も同様に。(土台部分を欠いてあるので、変則的な形です。)

今回は四角のままではなく、
丸のこで八角形に落とすことにしました。


最後に鉋で仕上げていきます。

大きな材料や、変則的な形のものは、鉋で仕上げるほかありません。
真っ平らにするのは、難しいです。
幅が広ければ、一発で仕上がらないので、
ずらしながら削っていくわけですが、
その際段差ができないように、研ぎで調整するのです。

枝の部分は節と言って、とてもかたい。

鉋は削る方向があります。
しかし、今回のように節がある場合、逆から削ります。
逆から削ると、今度は逆目と言って、
ボソボソなってしまう可能性があるので、
これを鉋の刃を調整しておさえます。
言葉だけではイメージし辛いかもしれません。
(「削る」と言う一つの作業ですが、
奥が深いと言う事がわかっていただけたでしょうか。)
本日も読んでいただきありがとうございます。
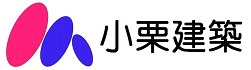
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
今回LDKが広いので、キッチン横に大黒柱を配置しました。
搬入された柱は荒木と言って、
大雑把に製材した状態で搬入されてきます。(一番右)
普通の柱の4本分の太さがあります。
まずは下処理
柱には、化粧面が乾燥して割れてしまわないように
「背割り」と言って、わざと切り込みを入れてあります。
年月が経過すると、その切込みが広がるように柱が動くので、
くさびを打って、事前に広げておきます。
余分な部分を切り落とし、
手押しと自動(大型の機械)で形を整えます。
そこに溝をついて、
埋木してあげます。
下処理が終わったら墨付けです。
ほぞを付けてあげます。(これは上の部分で梁にささります。)
下も同様に。(土台部分を欠いてあるので、変則的な形です。)
今回は四角のままではなく、
丸のこで八角形に落とすことにしました。
最後に鉋で仕上げていきます。

大きな材料や、変則的な形のものは、鉋で仕上げるほかありません。
真っ平らにするのは、難しいです。
幅が広ければ、一発で仕上がらないので、
ずらしながら削っていくわけですが、
その際段差ができないように、研ぎで調整するのです。

枝の部分は節と言って、とてもかたい。

鉋は削る方向があります。
しかし、今回のように節がある場合、逆から削ります。
逆から削ると、今度は逆目と言って、
ボソボソなってしまう可能性があるので、
これを鉋の刃を調整しておさえます。
言葉だけではイメージし辛いかもしれません。
(「削る」と言う一つの作業ですが、
奥が深いと言う事がわかっていただけたでしょうか。)
本日も読んでいただきありがとうございます。
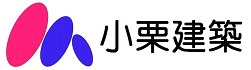
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
2017年11月10日 20:42
垂木≫
カテゴリー │中区H・U様邸
U様邸
続いて垂木の加工を紹介します。
今回垂木は8種類の長さがあります。
同じ長さのものをまとめて加工します。
材料のいい部分を使うように、
一本一本目で確認し、並べていきます。

長さを切りそろえ、釘穴をあけていきます。


種類ごとに、建前で施工しやすいように梱包します。(写真手前)

垂木は、屋根によってさまざまな角度・長さで切断します。
長さの出し方は公式のようなものがあります。
屋根の構成を把握し、
それに公式をあてはめながら墨を付けていくんです。
計算には電卓が必須です。
余談ですが・・・
高校の時に計算技術検定と言うのを受けました。
関数電卓を駆使して問題を解いていく検定です。
3級はクラス全員とれるくらいのレベルですが、
2級は正直なんの計算をしているのかよくわからぬままやっていました。
1級ともなると、数学の先生でもちょっと、、と言うレベル。
当時は使い道はなさそうな資格だなと思っていましたが、
屋根は3Dで長さを出していくので、
計算技術検定で電卓の使い方を学んでおいてよかったなと感じています。
本日も読んでいただきありがとうございました。
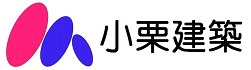
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
続いて垂木の加工を紹介します。
今回垂木は8種類の長さがあります。
同じ長さのものをまとめて加工します。
材料のいい部分を使うように、
一本一本目で確認し、並べていきます。
長さを切りそろえ、釘穴をあけていきます。
種類ごとに、建前で施工しやすいように梱包します。(写真手前)
垂木は、屋根によってさまざまな角度・長さで切断します。
長さの出し方は公式のようなものがあります。
屋根の構成を把握し、
それに公式をあてはめながら墨を付けていくんです。
計算には電卓が必須です。
余談ですが・・・
高校の時に計算技術検定と言うのを受けました。
関数電卓を駆使して問題を解いていく検定です。
3級はクラス全員とれるくらいのレベルですが、
2級は正直なんの計算をしているのかよくわからぬままやっていました。
1級ともなると、数学の先生でもちょっと、、と言うレベル。
当時は使い道はなさそうな資格だなと思っていましたが、
屋根は3Dで長さを出していくので、
計算技術検定で電卓の使い方を学んでおいてよかったなと感じています。
本日も読んでいただきありがとうございました。
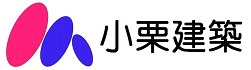
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
2017年11月08日 17:30
束・柱の刻み≫
カテゴリー │中区H・U様邸
U様邸
母屋の加工が終われば、束の刻みです。
束とは、母屋を支える短い柱です。
母屋の切れ端が出るので、
材料を余すところなく使えるよう考えながら墨を付けています。
その切れを使い切って、足らずを注文すると言った具合です。
無駄が極力発生しないようにしています。
続いて柱が搬入されました。
6mの通し柱

4mの柱と大黒柱

3mの柱

既製品の柱は決まった長さなので、
これも無駄が無いように割り振ります。
一本一本、反りやねじれの具合を見ながら
配置を決めて墨をしていきます。
上に積まれているのが柱です。
長さがいろいろあるのがわかると思います。

ホゾは長くしたいです。梁の欠きとの具合を見ながらです。
かたく組み上げる感覚は、
建前を体験してもらわないと実感できないと思うので、
この良さを一般の方に伝えるのがなかなか難しい。
いろいろな意見がありますが、
机上と現場の差があるように感じる時もあります。
本日も読んでいただきありがとうございます。
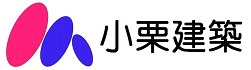
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
母屋の加工が終われば、束の刻みです。
束とは、母屋を支える短い柱です。
母屋の切れ端が出るので、
材料を余すところなく使えるよう考えながら墨を付けています。
その切れを使い切って、足らずを注文すると言った具合です。
無駄が極力発生しないようにしています。
続いて柱が搬入されました。
6mの通し柱
4mの柱と大黒柱
3mの柱
既製品の柱は決まった長さなので、
これも無駄が無いように割り振ります。
一本一本、反りやねじれの具合を見ながら
配置を決めて墨をしていきます。
上に積まれているのが柱です。
長さがいろいろあるのがわかると思います。
ホゾは長くしたいです。梁の欠きとの具合を見ながらです。
かたく組み上げる感覚は、
建前を体験してもらわないと実感できないと思うので、
この良さを一般の方に伝えるのがなかなか難しい。
いろいろな意見がありますが、
机上と現場の差があるように感じる時もあります。
本日も読んでいただきありがとうございます。
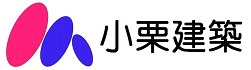
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
2017年11月07日 21:08
母屋の刻み≫
カテゴリー │中区H・U様邸
U様邸
梁の刻みが終わったら、
次は母屋(もや)の刻みです。
これは、屋根を構成する材料です。
今回は切妻屋根です。
高さがいろいろなので、特殊な寸法の部分もあり、注意が必要です。

垂木(斜めにかける材料)の切り欠きが455mmピッチに刻まれていきます。

定規をつくるので、墨としてはこれだけです。
起りや照りの場合、
定規を調整しながら、口脇の勾配を変えて加工します。

最近は切妻か片流れがほとんどです。
寄棟や入母屋屋根になると、加工がもっと複雑になります。
本日も読んでいただきありがとうございます。
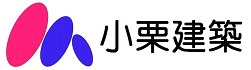
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
梁の刻みが終わったら、
次は母屋(もや)の刻みです。
これは、屋根を構成する材料です。
今回は切妻屋根です。
高さがいろいろなので、特殊な寸法の部分もあり、注意が必要です。
垂木(斜めにかける材料)の切り欠きが455mmピッチに刻まれていきます。
定規をつくるので、墨としてはこれだけです。
起りや照りの場合、
定規を調整しながら、口脇の勾配を変えて加工します。
最近は切妻か片流れがほとんどです。
寄棟や入母屋屋根になると、加工がもっと複雑になります。
本日も読んでいただきありがとうございます。
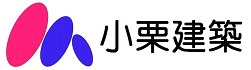
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
2017年11月05日 14:32
梁の刻み≫
カテゴリー │中区H・U様邸
中区U様邸
作業場では刻みを進めています。
土台の次は梁です。
まずは墨付けです。

次は刻んでいきます。


今回一番大きい材料は高さが36㎝です。

化粧材と言って、「木を仕上がりとしておさめる部分」は綺麗に削ってあげます。
これは搬入された時の状況。
ぼこぼこしています。(昔はもっと荒いです)


今回はヤスリで削りました。
平になったのがわかると思います。


一旦積み上げて、
全て刻んだら並べ直して梱包します。

加工の内容はのちのち紹介したいと思っています。
本日も読んでいただきありがとうございます。
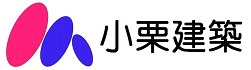
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
作業場では刻みを進めています。
土台の次は梁です。
まずは墨付けです。
次は刻んでいきます。
今回一番大きい材料は高さが36㎝です。
化粧材と言って、「木を仕上がりとしておさめる部分」は綺麗に削ってあげます。
これは搬入された時の状況。
ぼこぼこしています。(昔はもっと荒いです)
今回はヤスリで削りました。
平になったのがわかると思います。
一旦積み上げて、
全て刻んだら並べ直して梱包します。
加工の内容はのちのち紹介したいと思っています。
本日も読んでいただきありがとうございます。
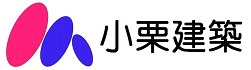
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
2017年11月04日 19:42
ここまでくると、いよいよ私たち大工の出番です。
本日も読んでいただきありがとうございます。
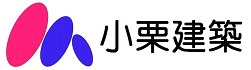
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
工事本格始動≫
カテゴリー │中区H・U様邸
中区U様邸
地鎮祭(工事の無事と家建物の繁栄を祈る儀式)を行いました。

それが終わるといよいよ新築工事が本格的に始まります。
狭い場所の配管や、外構工事として一部ブロックを施工しました。
広いうちにやる方が、安全で効率が良いからです。
そして基礎工事開始です。
私たちは、境界線からの位置や、基準となる高さの確認に立ち会います。
さらに、土台の継ぎ手などに不具合がでないよう
ボルトの位置や、人通口の位置など、確認します。
基礎と骨組みが合致していなければ、意味がありません。
これは高さを見る機械です。

覗くとこんな感じ(うまくとれませんでした)

糸をはって位置出しです。

鋼製の型枠を使います。

完成した状況。
元左官屋さんの鏝捌きです。

地鎮祭(工事の無事と家建物の繁栄を祈る儀式)を行いました。
それが終わるといよいよ新築工事が本格的に始まります。
狭い場所の配管や、外構工事として一部ブロックを施工しました。
広いうちにやる方が、安全で効率が良いからです。
そして基礎工事開始です。
私たちは、境界線からの位置や、基準となる高さの確認に立ち会います。
さらに、土台の継ぎ手などに不具合がでないよう
ボルトの位置や、人通口の位置など、確認します。
基礎と骨組みが合致していなければ、意味がありません。
これは高さを見る機械です。
覗くとこんな感じ(うまくとれませんでした)
糸をはって位置出しです。
鋼製の型枠を使います。
完成した状況。
元左官屋さんの鏝捌きです。
ここまでくると、いよいよ私たち大工の出番です。
本日も読んでいただきありがとうございます。
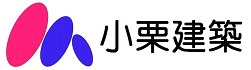
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp
2017年11月03日 10:03
解体完了≫
カテゴリー │中区H・U様邸
中区U様邸
既存住宅の解体工事がはじまったところでとまっているので、
その続きを書いていきたいと思います。
(カテゴリーで「中区H・U様邸」を選択していただくと、
その現場のブログに絞って表示できます。)
飛散防止用の囲いができたので、
重機を入れて解体していきます。

重機でバリバリと壊していくわけですが、
その操作はとてもやさしいです。
高い部分や、人力での解体が困難の部分を重機でやさしく降ろして、
そこからは手作業で分別して処理するからです。
それと、埃が舞い上がって、近隣へ飛散しないようにです。

解体が終わると、整地して完了です。


浜松駅周辺は、戦争の残骸を埋め立ててある場所があるそうです。
土地を買う時は、その場所の歴史を調べなければいけないですね。難しい。。
既存住宅の解体工事がはじまったところでとまっているので、
その続きを書いていきたいと思います。
(カテゴリーで「中区H・U様邸」を選択していただくと、
その現場のブログに絞って表示できます。)
飛散防止用の囲いができたので、
重機を入れて解体していきます。
重機でバリバリと壊していくわけですが、
その操作はとてもやさしいです。
高い部分や、人力での解体が困難の部分を重機でやさしく降ろして、
そこからは手作業で分別して処理するからです。
それと、埃が舞い上がって、近隣へ飛散しないようにです。
解体が終わると、整地して完了です。
浜松駅周辺は、戦争の残骸を埋め立ててある場所があるそうです。
土地を買う時は、その場所の歴史を調べなければいけないですね。難しい。。
2017年10月16日 18:16
宅地建物取引士≫
カテゴリー
日曜日、「宅建」試験、受けてきました。

たまたま土地の取引に関わることがあり、
土地家屋調査士の方や、
司法書士の方との会話に疑問が多く、
最低限の知識が必要と思ったのがきっかけです。
去年は3点足りず、
今年は2度目の受験でしたが、
最後の最後まで勉強をやり切った感がないまま
試験を受けてきました。
法律用語は理解に時間がかかり、
実務的にもほとんど関わったことのない内容なので、大変です。
去年の問題集も使いながら、今回使用したテキストがこちら。

あんまり手広くやらない方が良いと思っていましたが、
別の参考書で解説が少し変わるだけで、
スッと理解できたりするので、不思議です。
解答速報では、ぎりぎり合格ラインですので、
一安心ですが、結果発表までモヤモヤです。

4月ごろから少しずつ勉強をはじめ、
家族や仕事関係の方から協力をいただきながら、進めてきました。
いろいろなことが止まっている状況なので、
これから少しずつ再開していきます。
来年は1級建築施工管理技士の実務経験が解禁されるので、
そちらを受ける予定です。
宅建は最悪落ちていても、一旦お預けかな。
現場を進める上では経験に勝るものはないと思いますが、
技術だけあっても、知識がなければ、
(例えば)違法建築になってしまう可能性があります。
逆に知識だけあっても、
それを形にする技術がなければ意味がありません。
...なんて思いながらやっています。
結果が出たら、また報告したいと思います。
<主な資格>
2級建築士
1級建築大工技能士
2級施工管理技士
コンクリート技士
危険物取扱者 乙4
福祉住環境コーディネーター2級
ファイナンシャルプランナー3級
<技能講習>
ガス溶接
玉掛け
フォークリフト
小型移動式クレーン
<作業主任者>
木造組立等作業主任者
木材加工用機械作業主任者
足場の組立解体変更等作業主任者
鉄骨組立等作業主任者
<特別教育>
職長・安全衛生責任者
第2種酸素欠乏危険作業
低圧電気取扱作業
高所作業者運転業務
丸ノコ
<その他>
住宅省エネルギー技術者講習(施工・設計)
Microsoft Office Specialist(excel)
本日も読んでいただきありがとうございました。
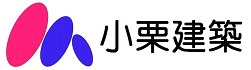
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp

たまたま土地の取引に関わることがあり、
土地家屋調査士の方や、
司法書士の方との会話に疑問が多く、
最低限の知識が必要と思ったのがきっかけです。
去年は3点足りず、
今年は2度目の受験でしたが、
最後の最後まで勉強をやり切った感がないまま
試験を受けてきました。
法律用語は理解に時間がかかり、
実務的にもほとんど関わったことのない内容なので、大変です。
去年の問題集も使いながら、今回使用したテキストがこちら。

あんまり手広くやらない方が良いと思っていましたが、
別の参考書で解説が少し変わるだけで、
スッと理解できたりするので、不思議です。
解答速報では、ぎりぎり合格ラインですので、
一安心ですが、結果発表までモヤモヤです。

4月ごろから少しずつ勉強をはじめ、
家族や仕事関係の方から協力をいただきながら、進めてきました。
いろいろなことが止まっている状況なので、
これから少しずつ再開していきます。
来年は1級建築施工管理技士の実務経験が解禁されるので、
そちらを受ける予定です。
宅建は最悪落ちていても、一旦お預けかな。
現場を進める上では経験に勝るものはないと思いますが、
技術だけあっても、知識がなければ、
(例えば)違法建築になってしまう可能性があります。
逆に知識だけあっても、
それを形にする技術がなければ意味がありません。
...なんて思いながらやっています。
結果が出たら、また報告したいと思います。
<主な資格>
2級建築士
1級建築大工技能士
2級施工管理技士
コンクリート技士
危険物取扱者 乙4
福祉住環境コーディネーター2級
ファイナンシャルプランナー3級
<技能講習>
ガス溶接
玉掛け
フォークリフト
小型移動式クレーン
<作業主任者>
木造組立等作業主任者
木材加工用機械作業主任者
足場の組立解体変更等作業主任者
鉄骨組立等作業主任者
<特別教育>
職長・安全衛生責任者
第2種酸素欠乏危険作業
低圧電気取扱作業
高所作業者運転業務
丸ノコ
<その他>
住宅省エネルギー技術者講習(施工・設計)
Microsoft Office Specialist(excel)
本日も読んでいただきありがとうございました。
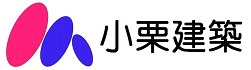
根っからの職人46年の父と、ゼネコンでの監督経験のある息子、
共に国家資格「建築大工一級技能士」です。
私たちは、設計(建築士)から現場の管理(施工管理技士)、
そして大工(技能士)をこなしつつ、
現場主義で日々の作業や思いをこのブログで発信しています。
住宅の新築、増築、リフォームはもちろん、
神社や店舗などの施工実績もあります。
木造建築のことでお困りでしたら、ぜひご相談下さい。
メール:ogurikenchiku@outlook.jp




